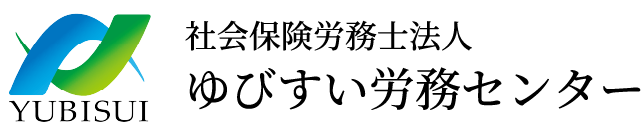2025.07.02
経歴詐称 ― 裁判事例から考える企業の対応
経歴詐称は、採用や派遣の現場で時に問題となります。
最近では派遣元企業が社員に虚偽の経歴を強要し、大手企業に派遣した結果、
社員が精神疾患を発症したとして訴訟に発展する事案が注目を集めています。
この裁判の経緯と、経歴詐称が発覚した場合の企業の対応について考えます。
派遣元による経歴詐称の強要
この事件は、未経験の男性を「職歴5年のエンジニア」と偽って派遣したことに端を発します。
派遣先で業務についていけず、男性は精神疾患を発症し退職に追い込まれました。
裁判で会社側は「IT業界では経歴詐称は一般的」と主張しましたが、当然認められず、取引先に対する詐欺行為とされました。
判決と賠償額の増額
一審判決では、会社側に254万円の賠償命令。その後控訴審で元社員の逸失利益も認められ、賠償額は336万円に引き上げられました。
現在は上告中ですが、上告審は事実認定を見直さないため、逆転は難しいと見られています。
弱り目に祟り目とはまさにこのことです。
経歴詐称の定義と企業対応
経歴詐称とは、
虚偽の学歴・職歴・資格を申告すること
本当の経歴を隠すこと
を指します。多くの企業では就業規則に経歴詐称を懲戒対象として明記しており、場合によっては懲戒解雇も可能です。
処分の判断基準
ただし、「程度による」という点が重要です。
詐称の悪質性
企業秩序への影響
を総合的に判断しなければなりません。経歴詐称が発覚したからといって、直ちに重い懲戒処分が妥当とは限りません。
冷静な対応の必要性
経歴詐称が明らかになったとき、感情的に強い叱責をすると別の問題を生む恐れがあります。
冷静かつ客観的に状況を判断し、適切に対応する姿勢が企業には求められます。
名古屋支店
特定社会保険労務士 山口征司
お問い合わせはこちらから
👉https://yubisui-r.jp/contact/