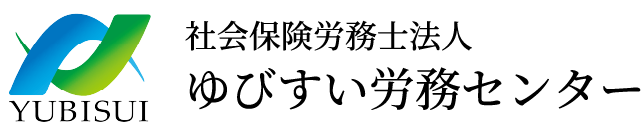2025.08.08
お金に働いてもらう時代へ。まずは一歩から。
日経新聞の記事によると、2024年にスタートした新NISAを機に、若い個人株主が増加しているようです。
2025年5月時点の株主数は約1,600万人で、新NISAが始まる直前の2023年12月と比較すると約100万人の増加。
これは、国民の8人に1人が株式投資をしている計算になります。
ただ逆に言えば、8人に7人はまだ株式投資をしていない(年齢的にできない人もいますが)という見方もでき、
金融機関や専門家がサポートできる余地はまだまだ大きいとも言えます。
社労士としての現場感:よくある投資の相談内容とは?
社労士の仕事をしていると、お客様からこの分野に関する質問を受けることがあります。
ただし、その内容にはある傾向があります。
たとえば――
「投資先をどう選べばよいか」(ほぼゼロ)
「始めてみたいけど、どう思いますか?」(多い)
「従業員が興味を持っているので、簡単に説明して欲しい」(増加中)
といった導入前の不安や関心レベルの質問が中心です。
投資未経験層の中に眠る“やってみたいけど…”層
つまり、8人中7人の中には、
「興味はあるけど、やり方が分からない」
「今すぐ始めるほどの動機付けがない」
といった、潜在的な投資希望者が一定数存在していると考えられます。
「全く興味がない」や「自分の意思でやっていない」層は、むしろ少数派のような印象さえ受けます。
国がNISAやiDeCoを推す本当の理由
ここ数年、NISAやiDeCoに関して、国は税制上の手厚い優遇措置を設けてまで、私たち国民に利用を強く促しています。
しかし、やたらと勧められると、逆に「何か裏があるのでは」と身構えてしまうのも消費者心理というものです。
その背景には、年金制度の限界があると考えられます。
そもそも年金制度は“賦課方式”
日本の公的年金制度は「賦課方式」と呼ばれ、
現役世代が高齢者の年金を支える仕組みになっています(※反対は積立方式)。
この構造上、少子高齢化が進行する現在では、制度自体の持続性に限界が見え始めているのが実情です。
その結果、
年金の支給開始年齢の引き上げ
年金支給額の見直し(減額)
といった議論はもはや絵空事ではなく、現実的な選択肢として浮上しています。
だからこそ「自助努力による資産形成」が求められている
そんな中で登場したのが、NISAやiDeCoなどの自助努力を促す制度です。
これらは制度の仕組みを理解し、自分に合った使い方をすれば、非常に大きなメリットがあることも確かです。
正しく使えば、実は“デメリットらしいデメリット”がほとんど見当たりません。
「誰かが導いてくれるならやってみたい」あなたへ
前述のように、「誰かが導いてくれるのであればやってみたい」と感じている方は少なくありません。
以前のコラムでも触れた通り、分からないことはファイナンシャルプランナー等の専門家に相談することが、
最初の一歩を踏み出すには非常に有効です。
必要なのは、「よく分からない」を「なるほど」に変えるちょっとした伴走者の存在かもしれません。
名古屋支店
特定社会保険労務士 山口征司
とはいえ、どこに相談すればいいのか分からない方は、まずはお気軽にご相談ください
👉https://yubisui-r.jp/planning/