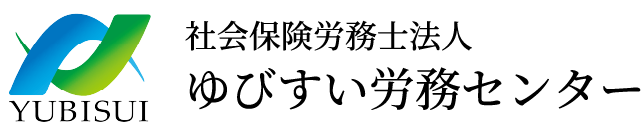2025.07.30
従業員の住宅事情と企業の責任
~「初任給は上がっても、一人暮らしできない」時代に~
初任給は上昇中、しかしそれ以上に家賃が高騰
ここ数年、新卒採用者の初任給水準は上昇を続けています。
しかし、それ以上のペースで上昇しているのが、単身者向け賃貸物件の家賃です。
この現実は、これから一人暮らしを始めようとする若手社会人にとって厳しいものですが、
実は企業にとっても深刻な問題です。
賃金改善が「焼け石に水」になっていないか
企業としては、人材確保のために基本給の引き上げや各種手当の拡充を図っています。
しかし、それ以上に生活コストが上がってしまえば、従業員がその恩恵を感じにくくなってしまいます。
「せっかくの賃上げが、家賃に消える」という声も少なくありません。
住宅手当の限界と従業員の実感
多くの企業では、住宅手当として月数千円〜数万円程度を給与に上乗せしています。
しかし、住宅手当は課税・社会保険料の対象となるため、実質的な手取り額にダイレクトに反映されません。
また、支給額に比べて家賃負担が重すぎるケースも多く、
「支給されている実感が薄い」と感じる従業員も少なくありません。
いま注目される社宅制度
こうした状況を背景に、企業によっては社宅制度の導入・見直しを進めています。
主な形態は以下の2つです
◎ 社有社宅
企業が所有する物件を、従業員に貸与する制度です。
建物の管理は自社で行い、固定資産税の納付義務などがありますが、自由度の高い運用が可能です。
◎ 借り上げ社宅
民間の賃貸物件を企業が借り上げ、従業員に提供する形です。
UR都市機構なども法人契約を促進しており、導入のハードルは比較的低いのが特徴です。
住宅支援は「求職者に選ばれる企業」への一歩
初任給が多少上がったとはいえ、若手にとって家賃負担は依然として大きな壁です。
そのなかで、住宅に関する支援制度を整えている企業は、求職者にとって非常に魅力的に映る可能性があります。
人材不足に悩む企業ほど、住環境のサポートに目を向ける価値は大いにあるでしょう。
社宅制度は就業規則・社会保険の扱いに注意
なお、社宅制度には税法上・社会保険上の取り扱いルールがあります。
たとえば、「賃料相当額の計算」や「課税・非課税の判定」など、
適切に運用しないと従業員に不利益を与えることにもなりかねません。
また、既存の住宅手当制度を廃止・変更する場合には、就業規則の改正も必要です。
社労士としてのご提案
住宅支援制度は、人材確保と定着に直結する“攻め”の施策である一方で、制度設計や運用には法的な配慮が欠かせません。
社宅制度の新設・見直しや、住宅手当との組み合わせ方は就業規則に落とし込む必要があります。
「人が集まる職場づくり」の一環として、住宅施策の見直しを始めてみませんか?
名古屋支店
特定社会保険労務士 山口征司
就業規則、給与規程の改正のご相談はこちらから
各種お問い合わせはこちらから
👉https://yubisui-r.jp/contact/