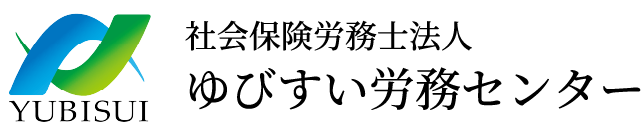2025.10.06
助成金は正しく使うもの ― 不正受給が招くリスクとは
コロナ禍で注目を集めた雇用調整助成金ですが、残念ながら不正受給のニュースも後を絶ちません。
令和7年6月末時点で、不正受給額は1,044億円に上り、企業経営や信用を脅かす大きな問題となっています。
今回は、助成金の本来の目的と、不正受給のリスクを整理します。
コロナ禍の雇用調整助成金、不正受給が1,044億円
厚生労働省の集計によると、特例的に拡充された雇用調整助成金の不正受給は、
令和7年6月末時点で1,044億円に達しました。
背景には、
申請数が膨大
給付のスピード優先で手続きが簡素化
といった事情があり、不正受給の温床となったと考えられます。
不正受給のうち、これまでに延滞金などを含めて約804億円が回収されています
最高額は京都の企業による49億円の不正受給で、既に返還済みとのことですが、「返せるんかい!」と言いたくなります。
そもそも助成金とは
助成金とは、国や自治体が特定の取り組みを支援するために交付する返済不要のお金です。主な特徴は以下の通りです。
返済不要:融資とは違い、原則返す必要なし
目的が限定:雇用改善、人材育成、設備投資、研究開発など政策目的に沿ったもの
要件遵守が必要:申請だけでなく、支給後も雇用維持や報告義務がある
申請主義:申請しなければもらえない
不正受給が後を絶たない現状
以前のコラムでも触れましたが、助成金は取り組みと主旨が合致した場合に活用するものです。
受給自体を目的に「寄せすぎた」場合、返還を求められるケースも少なくありません。
都道府県別では、私の住む愛知県が574件で最多、次いで東京、大阪、神奈川と続きます。
不正の手口には、休業日数の水増しや実際に支払っていない休業手当の虚偽申請などがあり、刑事事件に発展したケースも報告されています。
そしてそれらの不正を社会保険労務士が指南していたケースもあり、嘆かわく由々しき事態だと思います。
不正受給は犯罪行為
「運悪く見つかっただけ」と考える経営者もいますが、不正受給は立派な犯罪行為です。
助成金は税金を原資としている
虚偽申請は詐欺罪に問われる可能性
会社名や代表者名の公表など社会的信用の失墜リスク
ですので、無理に助成金を追いかけるのは非常に危険です。
助成金は正しく活用
助成金は、経営や採用計画を支える強力なツールです。しかし、自社の状況と助成金の趣旨が合致した場合のみ活用することが基本です。
不安な場合や申請方法に迷った場合は、私どもにご相談ください。
名古屋支店
特定社会保険労務士 山口征司
助成金についてはこちらから
👉https://yubisui-r.jp/subsidies/
お問い合わせはこちらから
👉https://yubisui-r.jp/contact/